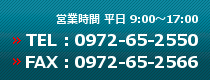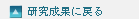
収益還元法の問題点
1. 収益還元法
収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより、その不動産の収益価格を求める手法です。不動産鑑定評価基準は、対象不動産の収益価格を求める手法について、次のように規定しています。
収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより、その不動産の収益価格を求める手法です。不動産鑑定評価基準は、対象不動産の収益価格を求める手法について、次のように規定しています。
| 収益価格を求める方法には、一期間の純収益を還元利回りによって還元する方法(以下「直接還元法」という )と、連続する複数の期間に発生する純収益及び復帰価格を、その発生時期に応じて現在価値に割り引き、それぞれを合計する方法(Discounted Cash Flow法(以下「DCF法」という )がある。 |
不動産鑑定評価業務を行う中で、不動産鑑定評価基準の上記の記述には大きな疑問を感じています。その部分とは、「収益価格を求める方法には、一期間の純収益を還元利回りによって還元する方法(以下「直接還元法」という )がある。」という記述です。直接還元法という手法は不動産鑑定評価の中で一定の認知を受けていますが、その手法を適用する不動産鑑定士は還元利回りについて暗中模索している状況なのです。
したがって、収益用不動産について説明力の高い不動産鑑定評価を行うとなれば、必然的に収益還元法としてDCF法を適用すべきであると考えます。ただし、不動産鑑定評価基準が規定しているDCF法にも大きな問題点があるのです。
したがって、収益用不動産について説明力の高い不動産鑑定評価を行うとなれば、必然的に収益還元法としてDCF法を適用すべきであると考えます。ただし、不動産鑑定評価基準が規定しているDCF法にも大きな問題点があるのです。
2. 直接還元法の問題点
直接還元法について、不動産鑑定評価基準は次のように規定しています。
不動産鑑定評価基準は還元利回りを求める方法として上記のように記載していますが、問題はこれらの方法で適切な還元利回りを求めることができるかということです。ここで「適切な」とは、例えば、「還元利回りがなぜ5.1%ではなく、5.3%でもなく、5.2%なのか」「還元利回りをどのように計算して求めたのか、その計算方法と採用数値は何か」などの開示請求に根拠を持って対応できるかということです。
結論から言いますと、これらの方法では適切な還元利回りを求めることはできません。銀行や外資系企業などが不動産融資や投資を行う場合に、「弊社は不動産投資においては年間純収益に対して4.5%の投資利回りを要求する」という主張の基に還元利回り4.5%を採用して収益価格を算定することは何も問題はありません。算定方法や採用数値に問題があろうがどうしようが、他人が口出しする問題ではないからです(もちろん、投資した資本が大きく毀損するようなことになれば、預金者や株主からは経営者責任を追求されるでしょうけど)。しかしながら、不動産鑑定士が確かな根拠無しに還元利回りの数値を採用して収益価格を算定することは、大きな問題を生じさせることになります。
直接還元法について、不動産鑑定評価基準は次のように規定しています。
| 直接還元法 |
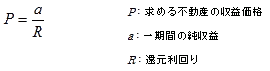 |
|
還元利回りは、直接還元法の収益価格及びDCF法の復帰価格の算定において、一期間の純収益から対象不動産の価格を直接求める際に使用される率であり、将来の収益に影響を与える要因の変動予測と予測に伴う不確実性を含むものである。 |
|
還元利回りを求める方法を例示すると次のとおりである。 (ア)類似の不動産の取引事例との比較から求める方法 この方法は、対象不動産と類似の不動産の取引事例から求められる利回りをもとに、取引時点及び取引事情並びに地域要因及び個別的要因の違いに応じた補正を行うことにより求めるものである。 (イ)借入金と自己資金に係る還元利回りから求める方法 この方法は、対象不動産の取得の際の資金調達上の構成要素(借入金及び自己資金)に係る各還元利回りを各々の構成割合により加重平均して求めるものである。 (ウ)土地と建物に係る還元利回りから求める方法 この方法は、対象不動産が建物及びその敷地である場合に、その物理的な構成要素(土地及び建物)に係る各還元利回りを各々の価格の構成割合により加重平均して求めるものである。 (エ)割引率との関係から求める方法 この方法は、割引率をもとに対象不動産の純収益の変動率を考慮して求めるものである。 |
不動産鑑定評価基準は還元利回りを求める方法として上記のように記載していますが、問題はこれらの方法で適切な還元利回りを求めることができるかということです。ここで「適切な」とは、例えば、「還元利回りがなぜ5.1%ではなく、5.3%でもなく、5.2%なのか」「還元利回りをどのように計算して求めたのか、その計算方法と採用数値は何か」などの開示請求に根拠を持って対応できるかということです。
結論から言いますと、これらの方法では適切な還元利回りを求めることはできません。銀行や外資系企業などが不動産融資や投資を行う場合に、「弊社は不動産投資においては年間純収益に対して4.5%の投資利回りを要求する」という主張の基に還元利回り4.5%を採用して収益価格を算定することは何も問題はありません。算定方法や採用数値に問題があろうがどうしようが、他人が口出しする問題ではないからです(もちろん、投資した資本が大きく毀損するようなことになれば、預金者や株主からは経営者責任を追求されるでしょうけど)。しかしながら、不動産鑑定士が確かな根拠無しに還元利回りの数値を採用して収益価格を算定することは、大きな問題を生じさせることになります。
3. DCF法の問題点
DCF法について、不動産鑑定評価基準は次のように規定しています。
さて、不動産鑑定評価基準が規定しているDCF評価式のどこに問題があるかわかるでしょうか? 答えを言いますと、DCF評価式の問題点とは、①割引率を一定としていること、②割引率の求め方、③復帰価格を求めること なのです(ここでは、正味純収益(NCF)の算定については触れません)。
(1)割引率を一定としていることの問題点
土地残余法の問題点で、地価公示方式の土地残余法について「割引率である基本利率Yを一定としていること」を問題点として指摘しました。ここでも全く同じことが言えるのです。そもそも割引率とは何でしょうか?不動産鑑定評価基準は、
DCF法について、不動産鑑定評価基準は次のように規定しています。
| DCF法 |
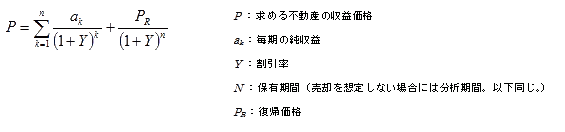 |
| 復帰価格とは、保有期間の満了時点における対象不動産の価格をいい、基本的には次の式により表される。 |
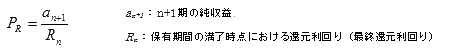 |
|
割引率を求める方法を例示すると次のとおりである。 (ア)類似の不動産の取引事例との比較から求める方法 この方法は、対象不動産と類似の不動産の取引事例から求められる割引率をもとに、取引時点及び取引事情並びに地域要因及び個別的要因の違いに応じた補正を行うことにより求めるものである。 (イ)借入金と自己資金に係る割引率から求める方法 この方法は、対象不動産の取得の際の資金調達上の構成要素(借入金及び自己資金)に係る各割引率を各々の構成割合により加重平均して求めるものである。 (ウ)金融資産の利回りに不動産の個別性を加味して求める方法 この方法は、債券等の金融資産の利回りをもとに、対象不動産の投資対象としての危険性、非流動性、管理の困難性、資産としての安全性等の個別性を加味することにより求めるものである。 |
さて、不動産鑑定評価基準が規定しているDCF評価式のどこに問題があるかわかるでしょうか? 答えを言いますと、DCF評価式の問題点とは、①割引率を一定としていること、②割引率の求め方、③復帰価格を求めること なのです(ここでは、正味純収益(NCF)の算定については触れません)。
(1)割引率を一定としていることの問題点
土地残余法の問題点で、地価公示方式の土地残余法について「割引率である基本利率Yを一定としていること」を問題点として指摘しました。ここでも全く同じことが言えるのです。そもそも割引率とは何でしょうか?不動産鑑定評価基準は、
| 割引率は、DCF法において、ある将来時点の収益を現在時点の価値に割り戻す際に使用される率であり、還元利回りに含まれる変動予測と予測に伴う不確実性のうち、収益見通しにおいて考慮された連続する複数の期間に発生する純収益や復帰価格の変動予測に係るものを除くものである。 |
と規定していますが、これではサッパリわかりません。還元利回りと似ているけどチョット違うよと言われても、わかりません。「還元利回り」を基本に据えて割引率を説明しようとしているため、さらなる混乱が生じるのです。順序が逆です。
不動産鑑定評価に用いる「割引率」とは、価格時点において予測される、将来正味純収益に対する資本調達コスト率なのです。金融債(利付債や割引債)の場合、満期までの期間が短く各年の収入額が確定しているため、分子の収入額は一定として分母の割引率にリスクを含めて考えますが、不動産(賃貸マンション、オフィス、ホテルなどの収益用不動産)の場合は各年の収入額は不確定であり稼働率などの変動による収入額の増減や継続性がリスクそのものを表しているため、割引率に不動産固有のリスクを含めず資本調達コスト率のみとした方が合理的なのです。そして、この将来正味純収益に対する資本調達コスト率は、遠い先の収益に対しては金利変動の不確実性が高まるため高いリターンが要求されることになるのです。したがって、不動産鑑定評価に用いる「割引率」は、一定ではなく、変動することを前提にすべきなのです。
(2)割引率の求め方の問題点
不動産鑑定評価基準は、「割引率」の求め方について上述のように規定しています。
(ア)類似の不動産の取引事例との比較から求める方法 は、現実に取引された類似不動産の取引価格(初期投資額)を基にIRR(内部収益率)を求め、その内部収益率から対象不動産の割引率を求める手法です。
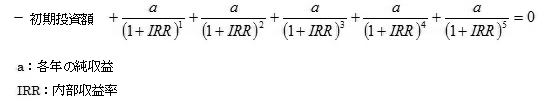
しかし、この方法では重要な情報である類似不動産の物理的劣化に対する評価やその他の要因をIRRの中に混入させ閉じ込めてしまうため、類似不動産の内部収益率から対象不動産の割引率を求めることが難しいのです。
(イ)借入金と自己資金に係る割引率から求める方法 は、借入金利率と自己資本割引率を資本調達割合に応じて加重平均して求める方法ですが、借入金利率は価格時点現在の平均的貸出金利であり、将来の金利変動リスクを含んでいないため将来純収益を割り引くために用いることは適切ではありません。また、自己資本割引率については投資家のスタンスにより異なり、また情報も無いため、適切な解を求めることができません。したがって、この方法も不動産鑑定評価に用いる「割引率」としては不適切なのです。
(ウ)金融資産の利回りに不動産の個別性を加味して求める方法 は、通常、新発10年国債の利回りに、対象不動産の投資対象としての危険性、非流動性、管理の困難性、資産としての安全性等の個別性をそれぞれ見積もって加算し割引率とする方法ですが、2年目、3年目、4年目・・・の純収益を期間10年のスポットレートである10年国債の利回りを構成要素とした割引率で割り引くことは不合理であり、また、対象不動産の投資対象としての危険性・非流動性・管理の困難性・資産としての安全性等をそれぞれ割引率構成数値として求めることは至難の業なのです。
では、不動産評価に用いる「割引率」をどのように求めるべきでしょうか。
割引率は、次の式で表せます。
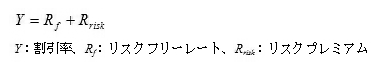
リスクフリーレートとは、リスクが極めて小さい商品の利回りのことをいいます。一般的にリスクフリーレートには、LIBOR(London Inter-Bank Offered Rate)やTIBOR(Tokyo Inter-Bank Offered Rate)などを用いますが、不動産評価の場合には40年先の値まである東京円金利スワップレート(変動金利である6ヶ月LIBORと、交換対象となる固定金利の交換レートのこと)を用いるのが適切と考えます。国債については、政府による資金調達という目的があるため、5年国債の利回りが他の期間の国債の利回りより相対的にやや高く、歪みがあるように感じます。
2012年6月1日15時時点における東京円金利スワップレートは、次のとおりです。
リスクプレミアム(Risk premium)とは、金融商品などの許容リスクに対して支払われる対価です。不動産取引等において融資しているのは国内銀行などの金融機関ですから、不動産評価においてはこれら金融機関が融資リスクに対して何%のリターンがないと納得しないかということを表しています。金融機関の行動は株式市場や預金者行動などを通じて評価されるため、不動産融資におけるリスクプレミアムは現実的な値に収束して定まります。リスクプレミアムの計算方法はいろいろあるのかもしれませんが、不動産評価においては、逆算的に比較的安定的な不動産ローンの固定金利からリスクフリーレートを控除することによって、リスクプレミアムの値を把握する方法が良いと考えています。
(3)復帰価格を求めることの問題点
不動産鑑定評価基準では、DCF法について、保有期間(投資期間)満了時点における「復帰価格」を求め、その「復帰価格」の割引現在価値と保有期間内における年間正味純収益(NCF)の割引現在価値を合計して収益価格を求めるとしています。また、「復帰価格」については、ターミナルレート(最終還元利回り)を求め、直接還元法により求めるとされています。問題は、このターミナルレートなのです。保有期間10年後(5年後でもいいですが)の個別不動産について確かな数値としてターミナルレートを求めることのできる不動産鑑定士はおそらくいないでしょう。なぜなら、価格時点においてさえも還元利回りを求めることは困難を極めるのに、10年後の様々な要因を縮約するターミナルレート(最終還元利回り)を確かな数値として求めることは、不可能といわざるをえないからです。 この場合、「では、どのようにして復帰価格を求めるのか」という問いが返ってくることは容易に予想できますが、私の答えは「復帰価格など求めない」です。後々、その理由と考え方を記載します。
不動産鑑定評価に用いる「割引率」とは、価格時点において予測される、将来正味純収益に対する資本調達コスト率なのです。金融債(利付債や割引債)の場合、満期までの期間が短く各年の収入額が確定しているため、分子の収入額は一定として分母の割引率にリスクを含めて考えますが、不動産(賃貸マンション、オフィス、ホテルなどの収益用不動産)の場合は各年の収入額は不確定であり稼働率などの変動による収入額の増減や継続性がリスクそのものを表しているため、割引率に不動産固有のリスクを含めず資本調達コスト率のみとした方が合理的なのです。そして、この将来正味純収益に対する資本調達コスト率は、遠い先の収益に対しては金利変動の不確実性が高まるため高いリターンが要求されることになるのです。したがって、不動産鑑定評価に用いる「割引率」は、一定ではなく、変動することを前提にすべきなのです。
(2)割引率の求め方の問題点
不動産鑑定評価基準は、「割引率」の求め方について上述のように規定しています。
(ア)類似の不動産の取引事例との比較から求める方法 は、現実に取引された類似不動産の取引価格(初期投資額)を基にIRR(内部収益率)を求め、その内部収益率から対象不動産の割引率を求める手法です。
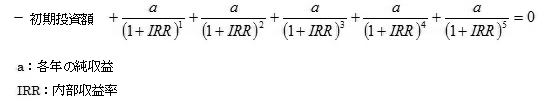
しかし、この方法では重要な情報である類似不動産の物理的劣化に対する評価やその他の要因をIRRの中に混入させ閉じ込めてしまうため、類似不動産の内部収益率から対象不動産の割引率を求めることが難しいのです。
(イ)借入金と自己資金に係る割引率から求める方法 は、借入金利率と自己資本割引率を資本調達割合に応じて加重平均して求める方法ですが、借入金利率は価格時点現在の平均的貸出金利であり、将来の金利変動リスクを含んでいないため将来純収益を割り引くために用いることは適切ではありません。また、自己資本割引率については投資家のスタンスにより異なり、また情報も無いため、適切な解を求めることができません。したがって、この方法も不動産鑑定評価に用いる「割引率」としては不適切なのです。
(ウ)金融資産の利回りに不動産の個別性を加味して求める方法 は、通常、新発10年国債の利回りに、対象不動産の投資対象としての危険性、非流動性、管理の困難性、資産としての安全性等の個別性をそれぞれ見積もって加算し割引率とする方法ですが、2年目、3年目、4年目・・・の純収益を期間10年のスポットレートである10年国債の利回りを構成要素とした割引率で割り引くことは不合理であり、また、対象不動産の投資対象としての危険性・非流動性・管理の困難性・資産としての安全性等をそれぞれ割引率構成数値として求めることは至難の業なのです。
では、不動産評価に用いる「割引率」をどのように求めるべきでしょうか。
割引率は、次の式で表せます。
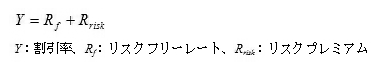
リスクフリーレートとは、リスクが極めて小さい商品の利回りのことをいいます。一般的にリスクフリーレートには、LIBOR(London Inter-Bank Offered Rate)やTIBOR(Tokyo Inter-Bank Offered Rate)などを用いますが、不動産評価の場合には40年先の値まである東京円金利スワップレート(変動金利である6ヶ月LIBORと、交換対象となる固定金利の交換レートのこと)を用いるのが適切と考えます。国債については、政府による資金調達という目的があるため、5年国債の利回りが他の期間の国債の利回りより相対的にやや高く、歪みがあるように感じます。
2012年6月1日15時時点における東京円金利スワップレートは、次のとおりです。
| 1.0年:0.345% | 1.5年:0.345% | 2.0年:0.346% | 3.0年:0.351% | 4.0年:0.370% | 5.0年:0.408% |
| 6.0年:0.466% | 7.0年:0.544% | 8.0年:0.636% | 9.0年:0.734% | 10.0年:0.833% | 12.0年:1.020% |
| 15.0年:1.253% | 20.0年:1.486% | 25.0年:1.576% | 30.0年:1.609% | 35.0年:1.648% | 40.0年:1.687% |
リスクプレミアム(Risk premium)とは、金融商品などの許容リスクに対して支払われる対価です。不動産取引等において融資しているのは国内銀行などの金融機関ですから、不動産評価においてはこれら金融機関が融資リスクに対して何%のリターンがないと納得しないかということを表しています。金融機関の行動は株式市場や預金者行動などを通じて評価されるため、不動産融資におけるリスクプレミアムは現実的な値に収束して定まります。リスクプレミアムの計算方法はいろいろあるのかもしれませんが、不動産評価においては、逆算的に比較的安定的な不動産ローンの固定金利からリスクフリーレートを控除することによって、リスクプレミアムの値を把握する方法が良いと考えています。
(3)復帰価格を求めることの問題点
不動産鑑定評価基準では、DCF法について、保有期間(投資期間)満了時点における「復帰価格」を求め、その「復帰価格」の割引現在価値と保有期間内における年間正味純収益(NCF)の割引現在価値を合計して収益価格を求めるとしています。また、「復帰価格」については、ターミナルレート(最終還元利回り)を求め、直接還元法により求めるとされています。問題は、このターミナルレートなのです。保有期間10年後(5年後でもいいですが)の個別不動産について確かな数値としてターミナルレートを求めることのできる不動産鑑定士はおそらくいないでしょう。なぜなら、価格時点においてさえも還元利回りを求めることは困難を極めるのに、10年後の様々な要因を縮約するターミナルレート(最終還元利回り)を確かな数値として求めることは、不可能といわざるをえないからです。 この場合、「では、どのようにして復帰価格を求めるのか」という問いが返ってくることは容易に予想できますが、私の答えは「復帰価格など求めない」です。後々、その理由と考え方を記載します。