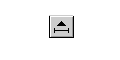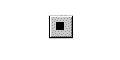『火車』 宮部みゆき
(平成十年二月一日発行・新潮社)
|
スナック強盗に改造拳銃で左膝を撃ち抜かれて休職中の刑事、本間を、亡き妻の親戚である青年が訪ねてくる。突然行方不明になった婚約者、関根彰子を捜してほしい、と。 失踪は、彰子が五年前に自己破産していた事実が露顕したことに端を発している。本間は自己破産の手続きをした弁護士を訪ね、思わぬ事態に遭遇する。彰子の写真を見た弁護士は、こういったのだ。 > 「この女性は、私の知っている関根彰子さんではありません。 > 会ったこともない。誰だか知らないが、 > この女性は関根彰子さんじゃありませんよ。 > 別人です。あなたは別人の話をしている」 (文中、傍線は引用者による) さて、この欄では毎回のように書いてるけど、『火車』は面白い小説です。かなりのヴォリュームですが、仕事がなければ一気に読んでいただろう本です。山本周五郎賞受賞の価値は充分にあります。 この小説の本当の主人公は、“関根彰子”だと思う。正確にいえば「関根彰子を乗っ取った女性」だけれども。あ、これちょっとネタばれかな。 読者は本間の眼を通して(一人称の小説ではないが、ものがたりは本間の行動を軸に展開する)、関根彰子であった女性の正体を掘り下げる作業に参加する。まるっきりの謎だった彼女の姿が、地道な作業と推理、いくつかの偶然によって、次第に明らかになってゆく。 なぜ、彼女は関根彰子になりすましたのか。なぜ、「自己破産」が露顕した瞬間、姿を消したのか。その動機が、理由が、小春日和の日に氷が溶けてゆくように、本当にゆっくりと明らかにされてゆく。 本間の視点を通して、という書きかたが、とにかくうまい。ほんの小さな発見、進歩が、さもおおごとかのように思わせる。もちろん、それらひとつひとつはすべて、“彼女の正体”に向けてのプロセスなのだけれども。 また、そのひとつひとつに対して、読者は本間と同じように推理する。「なぜ」、そうなったのか。そうしたのか。考える。次はどうすればいいか。どこへゆけばいいか。 その意味では、これは本格的な“ミステリィ”だともいえる。僕は普段ほとんどミステリィを読まないので、久しぶりに「ものがたりに併せてアタマを使用しながら」読む快感を味わった。 で、完全なネタばれになっちゃうので詳しくは書かないけれど、ものがたり後半の加速度もすごい。重要な鍵が発見されると同時に、一気に彼女の過去と動機が明らかにされていくのだ。「早く続きっ!」という気分でページを繰る手が止まらない。 あー、うまくまとまらないなあ。ともかく、特に中盤まで、多少饒舌すぎるきらいがなきにしもあらずだけれど、いい小説なのは間違いないです(と、僕は思います)。 最後に。解説でも触れられているが、宮部さんは(他の作品は読んでないので、この小説に限ってだけど)小さな表現の使い回しが実にうまいと思う。たとえば、こんな部分。“売られた後、逃げてきた”女性のことを、その友人が語るシーンだ。 > 「何があったのか、だいたいは想像がつきます。 > ただ、ひとつ不思議だったのは、彼女が、 > まるっきりなまものを食べることができなく > なってたことで・・・。(以下略)」 どうしてこれがうまいと思うかというと、表現は間接的なのに、「なにがあったのか」、(僕には)ひどくリアルに想像できてしまうことだ。そして、「想像がつきます」といっているにも関らず、それを「不思議」と思ってしまう友人。 結局、友人は“こちら側”の住人(それは、このものがたり中に幾人も登場するが)であって、“あちら側”の彼女を理解できることはないのだ。・・・こんな簡単な表現で、宮部さんはそこまでの対比をも伝えてしまう。これは女性ならではの描写だと思う。 そして“あちら側”の住人のほうが魅力的なのは、少なくともフィクションの世界においては事実なのであって・・・。僕は、できれば、どちら側の住人の気持ちをも理解できる人間でいたい、と思っている。 |