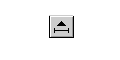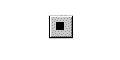『不夜城』 馳 星周
(平成十年四月二十五日初版発行・角川文庫)
|
台湾人の父と日本人の母をもつ高橋(劉)健一は、歌舞伎町に巣くう故買屋。
ある日、かつての仲間でいまは上海マフィアから追われる身となった男が、歌舞伎町に舞い戻ってきた。
そのため窮地に陥る健一。
さらに“夏美”と名のる謎の女もからみ、ものがたりは複雑化してゆく・・・。 この小説の登場人物は全員悪人だ。 あらゆる暴力、権力、権謀術数を使って自分が有利になるように立ち廻る。 その種類もつまらないチンピラから闇社会を牛耳るボスまで雑多にあるが、 どうもそいつの地位の高さと悪人度は比例してるように思える。 悪漢小説(ピカレスク ロマン)というのは、まさにこの小説のためにあるようなことばだ。 昨日まで、いや数分前まで仲間だった人間を平気で裏切り、売る奴ら。 騙されたほうも、もちろん報復する。すぐにそれができなくても、生きてる限りその念を胸に抱く。 この小説には、“ルール”ということばが頻出する。 ひとを殺したり、嘘をついたり苦しませたりすることが善だと教える宗教は、ない (すくなくともまっとうな宗教では)はずだ。 だが彼らの“ルール”のなかでは、それは自分が生き残るための、正統な手段となる。 > ところが本書『不夜城』には感情移入できる人間が > 一人としていない。主人公の健一はもちろんのこと、 > 脇を固める人物にいたるまで、読者の感情移入を > 拒否する人間ばかりだ。 北上次郎さんは、解説でそんなふうに書いている。 正直にいうと、僕はこの本を読んでいて気分が悪くなった。 ハードボイルドだろうとなんだろうと、ひとりくらいは善人がいてもいい。 シンパシィを感じる人間がいたほうがいい。 ところが馳星周は、それを完璧に拒絶している。 だけど、僕は読み進めざるをえなかった。 なにせ、ひさしぶりに自分の部屋に戻ってからも読み続けて (ふだん僕の読書時間は往復の通勤電車内の三十分。 おもしろいと感じた本に出会ったときだけ、それを超えることになる)、 結局一日で読破してしまったくらいだ。 そういう魅力が、たしかにこのものがたりには存在する。 この小説の魅力のひとつは、夏美だろう。 最初まったくの謎だった彼女の秘密がひとつずつ明らかになるにつれて、健一の視点 (一人称で描かれているゆえに、それは当然読者の視点とシンクロする) も少しずつ変わってゆく。 わずかずつにではあるが、好感のもてる人間のような気がしてくる。 ところが、だ。 ハードボイルド小説には、“主人公は死なない”という不文律がある (『逃れの街』のような例外も、たまにはあるが)。 絶体絶命のようでいてどこかに逃げ道がある。 それがあらかじめ伏線として蒔かれてるときもあるし、そうでないときもあるけれども。 クライマックス。 さあもうどこにも逃げられないぞどうするどうなる。 そこで、いきなり僕は落とし穴に落とされた。 そして、最終的に、この小説の登場人物で僕がシンパシィを感じる人間は、 ひとりもいなくなってしまったのだ。 だから、この小説を読み終わったとき、僕はまるで救われない気分だった。 わずかに最後の一行だけが心を繋いだが、時間が経つにつれて、それさえも実は別の意味だったんじゃないかと思えるようになってきた。 しかし読み終わったその夜は、すごい作品に出会ってしまったという興奮でなかなか眠れなかったことだけは、書いておく。 さて。この小説は映画化されるそうだ。 まあだいたい想像はつく。 ストーリィは変えられるだろう、それは間違いない。 そして、おそらく、よほど大胆なつくりかたをしなければ、ついに原作を超えられないだろうことも。 ただ、この作品の映像化を、一度観てみたいという気はする。 |