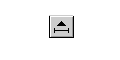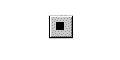『無能の人・日の戯れ』 つげ義春
(平成十年三月一日発行・新潮社文庫)
|
僕は某広告代理店に勤務しています。
代理店といってもD通とかH堂とかなんかとはまるっきり会社の規模が違いますが。 さて、うちの会社の売上の90%以上を占める最大クライアントが近年急成長してまして、以前はその会社の仕事はすべて無条件でうちにきていたのが、最近は部署毎に業者を選定するようになってきました。 そのうえ、儲かってるくせに経費削減を推し進めてまして、“いいものを”ってより、“とにかく安く!”って感じになっちゃってるんです。 そうすると、印刷物なんかは社内にデザイナーを抱えている大手の印刷会社のほうが安くあがりますし、展示会装飾なんかもデザインおかまいなしで、施工だけやってもらったほうが安い。 そのためうちの会社はひとつまたひとつと仕事を失っていっています。 で、ここのところ、ひとつプレゼンに敗けるたびに飲み屋で、 「M(最大クライアントの会社名)の仕事、ひとつも取れなくなったらどうしようかなあ・・・」 てな会話が交わされてるんですけど、そんなとき必ず社長が、 「よし、みんなで屋台のタコヤキ屋をひこう! 俺は新しいベンチャービジネスの先駆者になるぞ! お前は調布、お前は中野な」 と、冗談だとしたら笑えないし、本気だとしたらさらに笑えないことをいって、場がフリーズするんですが・・・。 さて、本題です。 『無能の人』の主人公は、むかしは有名な漫画家でした。 漫画家という稼業にゆきづまりを感じた彼は、中古カメラ屋や古物商などをやってみますが、いずれも失敗してしまいます。 ほとんど無一文同然となった彼は、“元手がいらないから”というだけの理由で、競輪場そばの多摩川の河原で、石屋をはじめます。 商売ものの石は、形は面白いものですが、いずれも河原で拾ったものばかり。 むろん彼の石を買ってゆくひとはまるでいません。 彼は知人に「あなたはなにもしていないのと同じだ」といわれてムッとします。 が、彼はいまだにごくたまにくるマンガやイラストの注文もすべて断り、どこかへ勤めようともしません。 夕方、子どもが彼を河原に迎えにきます。 > 「あの石 あのままで盗られないの」 > 「うん 盗む奴なんていないさ」 彼は、彼の石が売れるものではないことを、自らわかっているのです。 ただ、売りものにならない石を、売るふりをしているだけ。 そうそう、彼には奥さんと子ども(五歳くらいの男の子)がいます。 彼の生計を支えているのは、奥さんと子どもがビラくばりのアルバイトで得たわずかな、ほんとうにわずかなお金だけのようです。 孤独でないだけ、そして生活を支えてくれるひとのいるだけ、まだ彼は幸せなのかもしれません。 しかし奥さんはあるとき彼に、ふとこんなことをいいます。 > 「考えてみると私たちって 親しい友達もないし > 親兄弟とも疎遠だし なんだか世の中から孤立して > この広い宇宙に三人だけみたい」 ・・・と、こう書いてくると、彼らはものすごく悲惨な境遇にあるような感じがしますが、彼らには惨めさはあっても暗さは感じられない、と思うのは僕だけでしょうか。 会社がヤバくなったら、多摩川で石屋をやってみたい。 もちろん支えてくれるひとがいて、帰る家があって、そして自分の心が常にある部分オプティミスティックでなければ(それはすでにして、立派なひとつの才能ではありますが)、できる相談ではありませんけれども・・・。 というわけで、なんか仕事や人生に疲れたなあ、とお思いのあなた、ちょっとこの本を読んでみてはどうでしょう。 もっともそのせいで、あなたが僕より先に石屋さんになっちゃっても、僕は責任を負いませんけどね。 |