
|
花田清輝(1909−1974)。 主な著作に評論『復興期の精神』、『近代の超克』、小説『小説平家』、『鳥獣戯話』など。 例によって似てないです。でもまあ色塗るよりはマシだと思いましたので・・・。勘弁してください。 |
|
むかし、福岡県福岡市というところに、花田清輝という男がいた。後年『御伽草子』の一編に出てくる人物に自らを擬して『ものぐさ太郎』というエッセイを書いたくらいだから、そうとう怠惰な、そして一風変わった人間だったのだろうと思われる。 僕はこれからこのひとのはなしを、彼自身の手になる『ものぐさ太郎』に即して書いてみようと思うのだが・・・。実をいうと結末のメデタシメデタシの部分まで無事に辿り着けるかどうか、まるっきり自信がない。 というのも、僕自身が我々の主人公に負けず劣らずものぐさだからだ。もっとも、ものぐさでなければ職を離れて幾星霜、すでに失業保険も切られたというのに別段焦るでもなく、ぼーっと貯蓄を食い潰しているなんてことはしていまい。 しかし、まあ、そんなことはどうでもいい。とにかく、花田清輝は1926(大正15)年に旧制福岡中学校を卒業し、鹿児島の第七高等学校に入学する。現代のように高校が半ば義務教育とか猫も杓子も大学、という時代ではない。最終学歴が尋常小学校(いまでいえば小学校)卒というのが珍しくなかった頃だ。 しかも七高というのは当時でいうナンバースクール(東京の一高、熊本の五高などが有名)で、ここから帝大へ進むというのが当時のいわばエリートコースだった。いってみれば半ばエリートコースの指定席に乗っかったわけなのだが、どうやら彼の怠け癖はこのあたりから本格的にはじまったらしい。 福岡からやってきた清輝は、寮生活を送りはじめる(もっとも高等学校自体がほとんど存在しない時代だから、ほとんどの学生は寮生だったと思われるが)。 毎朝、授業開始のラッパの音を聴くと、寮生たちは慌てて起き出し、教室へと走ってゆく。しかし我々の主人公はその音を聴いても、いつも寮の一室にごろりと寝ころんだままでいた。 時にはラッパの音とともに起床することもあったが、そんなときでも彼の脚は決して教室へは向かわず、学校の裏手にある城山に向かった。そしてその頂上にやはりごろりと寝転び、飽かずぼーっと桜島を眺めていた。 『ものぐさ太郎』での記述「空は青かった」を見る限り、清輝少年は部屋で寝転ぶより城山の頂上で寝転ぶほうが多かったのではないかと思う。つまり晴れた日は城山、雨の日は寮の一室。 もっとも授業に出ないでごろりと寝転んでいることに変わりはない。彼は入学翌年の1927年、欠席多数を理由に落第。さらに翌年の1928年、同じ理由で二度目の落第をし、結局七高を退学(本人の謂によれば除名)している。 が、ここで問題にしたいのはどこで寝転ぶか、ということだ。わざわざ城山の頂上まで登るくらいなら、とりあえず寮からは圧倒的に近い教室までゆき、机にうつ伏せて眠ればいいではないか。 同じ寝るでもともかく出席は稼げる。移動の際のエネルギーの支出も少なくてすむのだから、我々の主人公は単にギルブレイスふうの動作研究を試みなかっただけであって、本来ものぐさではなかったという説もあるが、これは僕には承認しがたい。 というのも、僕にもかつて高校生活というものが存在した。一年の終わりに、クラスひとりひとりについて「寄せ書き」をすることになった。自分に贈られた「寄せ書き」を見ると、驚いたことにクラスメイト44名のうち実に10名以上が、僕の授業中の居眠りについて言及していたのだ。 つまり高校一年生の頃の僕は、それほど授業中によく居眠りをしている生徒だった。もしくは、本人にはまったくそんな自覚がないのだが、ともかく他の生徒にはそんなイメージが定着していたらしい。 ところが、三年になってからだ。僕は授業をサボって、その時間を校舎の屋上で過ごすことを覚えた。海は青かった。よく晴れた日には、視界の向こうにこの国で四番めに大きな島の影が、くっきりと見えた。 夏休みの補習の際には、二時間続けて嫌な科目ということもある。そんなとき、僕はわざわざ高校から歩いて15分の公園へ向かった。戦国時代には城だったので、小高い丘になっている。そこの見晴らしは、高校の校舎の屋上よりも断然素晴らしかった。 そう、屋上や公園で時を過ごすよりも授業や補習に出て居眠りしたほうが、エネルギーの支出は少ないし、リスクも小さいに決まっている。が、そのときの僕にあったのは単に“気持ちよさ”だった。 屋上や公園のベンチでごろりと寝転び、海を観て、ときには煙草を吸う。拘束のなかの、限りない自由。そしてその同じ瞬間、クラスメイトたちは狭く暗い教室で、面白くもない授業を聞いているのだ。それはまた、微かな、しかしまったく根拠のない優越感を、僕にもたらした。 閑話休題、はなしを元に戻さねばなるまい。花田清輝は、そういうわけで七高を退学となった。あくせく働く蟻を尻目に、ヴァイオリンも弾かずに寝転んでいたのだから仕方がない。なにせ服を着替えるのも面倒で、夜も制服のまま就寝していたというのだから、そのものぐさ度は半端ではない。 もっともこの寓話も、こんにちでは成立が危ぶまれている。先日の『こちら葛飾区亀有公園前派出所』では、両津巡査がそのラストを「ヴァイオリンを弾いていた蝉はスカウトされてCDデヴューし、その印税で余生を左団扇で暮らしました。蟻はリストラに遭って職を失い、のたれ死にました」と改変している。・・・ちょっと笑えないはなしだ。 我々の主人公はもちろん両津のようなしんからの享楽派ではなかっただろうが、ここでも一度、『こち亀』と同じことが起こった。ある日彼の住む寮が火事に遭い、寮生たちはとるものもとりあえず戸外へ避難した。 真夜中に出火したので他の寮生たちは寝間着一枚でぶるぶる震えていたが、清輝少年は就寝時にも学生服のままだったので、ひとり寒い思いをしなくて済んだという。もっともそれで痛快な思いを味わったというのだから、彼も当時は僕同様、あまりたいした人間ではなかったのかもしれない。 さて、七高を追い出された我々の主人公は、九州大学の聴講生を経て京都大学英文科選科へ進む。在学中公募の文学賞を受賞するが、授業料滞納で京大も馘に。その後さまざまな変遷を経て戦後売れっ子の評論家となり、吉本隆明と論争したりするのだが・・・。 しかし、ここでもう一度、閑話休題となってしまう。やはり一回ぶんのスペースでこのはなしをでっちあげるのは、いささか無理だったようだ。 いや、それよりなにより、なにしろパロディというのは、基本的には読者が元ネタを知らないと、成立しないものなのだ。いったい元ネタを知っているひとがなん人いるのだろう・・・。あー疲れた。 参考文献:花田清輝『もう一つの修羅』、 一九九一年二月一○日第一刷発行、講談社文芸文庫 |
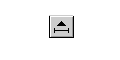
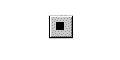
|
しろやま、と読みます。西南戦争最後の激戦地で、西郷隆盛の終焉の地として有名。 |