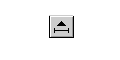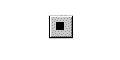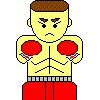
|
うわ、なんかぜんぜん似てねー。 友人のS君か、ただのやんきいの にいちゃんみたいだ。 ほんとの辰吉はもっと怖いぞ。 でも友達になりたいタイプでは ある。 |
|
岡山の不良少年が、チャンピオンに返り咲いた。 僕はボクシングにはあまり詳しくないけれども、 日本人の世界挑戦が十なん戦か連続で失敗しているということくらいは知っている。 同時に、なんとなく日本のボクシング界が最近焦っているように感じていた。 あれじゃ敗けるよな。 最近の日本人挑戦者たちは、 みんなチャンピオンになるほどの実績も、 テクニックも持っていない。 だいたいチャンピオンに相応しい顔をしていないじゃないか。 誰も彼も、そう思えてしまう。 そんななか、辰吉が世界挑戦するというはなしを聞いた。 『The Last Judgement』、最後の挑戦。 六年前。 僕は生涯最初の、そしていまのところ最後の、入院をしていた。 二週間ほどのベッド上の生活は、ひどく退屈だった。 自分がこれからどうなってゆくのか、まるでわからない。 そんな時期にもちょうど、重なっていた。 ある日の夜、隣室から「うおーっ!」という声が聴こえた。 よく喫煙室で一緒に煙草をふかすおじさんの声だ。 どうしたんだろう、僕は様子を見にいった。 暑い時期だったから、ドアは開けっ放しになっている。 「どうかしたんですか?」 おじさんは、TVを観ていた。 「辰吉がな、やったんだよ。やっぱりすげえ奴だなあ」 それは、辰吉がはじめて世界を獲った瞬間だった。 彼はそのとき、TVの画面のなかで、両手を大きく天に突き上げていたと思う。 自分より齢下でありながら、 世界の頂点というひとつのたしかな目的地に立ったこの男を、 僕は羨望の念を込めて見つめた・・・。 それからだ。“辰吉丈一郎”という名前が、僕の胸に深く、刻まれたのは。 そして、六年。 僕は、あの頃微かに憧れていた広告の世界の端っこで働くようになっていた。 十一月二十二日。 二十七歳の辰吉丈一郎は、敗ければ引退の覚悟で七度めの世界戦に臨んだ。 チャンピオン、タイのシリモンコンは二十歳、十七戦全勝。 なんとまだダウンを一度しか貰っていない。 <もう少し、軽い相手を選べばよかったのに・・・> 試合前、アナウンサーがシリモンコンのプロフィールを語ったとき、 僕はそう思った。 井岡なんか、わざわざフライ級に落としてまでベルトを欲しがったんだぞ。 試合開始。さすがは辰吉だ。 動きがいままで無惨に敗れ去っていった日本人チャレンジャーたちとは、まるで違う。 アンディ フグ同様、こいつとは喧嘩したくないと切実に思う。 しかし、チャンピオンもすごい。 パンチのかわしもうまいし、距離のとりかた、クリンチでの逃げかた、なにもかもが完璧に見える。 辰吉のパンチはなん度かクリーンヒットするが、すぐに倍の数のお返しをしてくる。 だが、減量に失敗したというシリモンコンは、打ち合いのなかでだんだん動きが鈍くなってきたように感じられた。 そして、5R。ついに辰吉は有効なボディからのラッシュで、シリモンコンからダウンを奪う。 なんてことないよ、というように、立ち上がるチャンピオン。 6R。チャンスと見えた辰吉の動きが、鈍くなる。 さすが無敗のチャンピオンだった。 一瞬の隙をついて、クリーンヒットをかましてゆく。 だが、辰吉は倒れない。 そして、7R。辰吉はふたたび、ラッシュをはじめる。 6Rで決められなかったシリモンコンが、逆に疲れてきたんだ。 それは、いままで僕が観てきたすべてのボクシングの試合のなかでも、ベストのファイトだったと思う。 辰吉にもシリモンコンにも、判定に持ち込もうという意志はまったく、感じられなかった。 チャンピオンは若さゆえに。 そして辰吉は、おそらく彼が正真正銘のファイターだからこそ。 辰吉とシリモンコンは、原始のボクシングのように、ひたすら打ち合った。 しかし、辰吉のボディが効いたのか、チャンピオンはこの試合二度めの、そして生涯三度めのダウンを喫する。 立ち上がったチャンピオンの貌からは、すでに闘志は消え失せているように見えた。 襲いかかる辰吉。 「いけえーっ、辰吉!」 僕は思わず、なん度もそう叫んでいた。 TVの画面に向かって叫ぶのは、三年まえの有馬記念での直線、トウカイテイオーがビワハヤヒデに並びかけたとき以来だった。 そして、レフェリーが試合を止めた。 辰吉が、まるで神に感謝するかのように、リング上にひざまづく。 そしてその瞬間、僕の眼からとめどなく涙があふれていた。 ひどく自然に。 TVを観ていて泣いたのは、やはり三年前の有馬記念で、トウカイテイオーが先頭でゴールに駆け込んで以来だった。 ベルトを巻き、子どものひとりを抱き、ひとりを肩車した辰吉の眼には、光るものがあった。 その光景に、僕はもう一度泣いた。 「俺にはボクシングしかないんです」 そういいきった男が、見事にチャンピオンに返り咲いた。 はじめてチャンピオンになったときよりも、その貌はひどくカッコよく、僕には思えた。 |